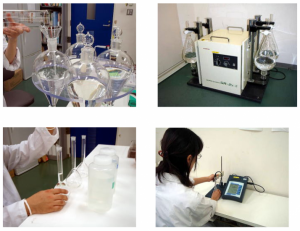西日本一帯で1968年に起きた食品公害「カネミ油症」。カネミ倉庫(北九州市)が製造した米ぬか油を口にした人が、強烈な倦怠(けんたい)感やめまい、皮膚炎などに襲われた。発生からすでに半世紀以上がたち、教科書で学んだ「過去の公害」と感じる人も多いだろう。しかし毒は今も被害者の体をむしばみ、苦しみは続いている。患者の子どもたちも同じような健康被害を訴えており、国も調査を始めた。救済を求める親子に話を聞いた。(共同通信=松本智恵)
▽顔は腫れ、息もできない
長崎県の五島列島で生まれ育った福岡県大牟田市の森田安子さん(68)。中学3年だった68年春、父親が近くの商店で買ってきたのがカネミ倉庫製の油だった。既に母親は他界し、父と妹2人、弟の5人暮らし。魚介の天ぷらを作るなどしてみんなで食べた。夏ごろ、急に顔が腫れあがり、ぜんそくのように苦しく息ができなくなった。ひどい倦怠(けんたい)感で寝たきりの日々。高校には進めず、看護師になる夢は諦めた。
近所の人にも同様の被害が出た。商店は「毒を売った店」と叩かれ、店主が謝罪に尋ねてきたのを覚えている。島で患者かどうか調べる集団検診があったが、寝たきりで受診できなかった。当時は皮膚症状を重視。妹2人と弟が受けると、黒い吹き出物がある2番目の妹だけが認定された。しかし認定されなかった妹は頻繁に倒れ、弟はぼうこう炎に悩まされ続けた。健康だった父は油を食べてから心臓が弱くなり、6年後に狭心症の発作で階段から落ちて亡くなった。
「当時、自分は原因不明の体調不良だと思いこんでいた」。患者認定された妹と自分では全く症状が違う。「当時はネットもない。油症についての情報が全くなかった」。その後、国が油症を「食中毒」と位置づけたことで「社会も『一時的な健康被害』と受け止め、次第に関心は薄れていった」。24歳の時に結婚し、子どもを望んだが3度の流産を経験した。悲しみを乗り越え一男二女に恵まれたが、倒れることも多く「思ったような子育てはできなかった」。子どもたちも成長するにつれ、倦怠感やぜんそくが現れてきた。
カネミ油を食べたことは夫に打ち明けてはいたが、「自分は患者ではないはず…」。ましてや油症が次世代にまで影響が及ぶものだとは全く知らなかった。転機となったのは2009年。油症患者を取り上げた新聞記事が目に入り「症状が自分にそっくりだ」と驚いた。新たな患者の認定基準には、ダイオキシン類の血中濃度が加わっていた。油症検診を受けると基準値の50を大きく上回る73・92。「自分もそうなのか」。油を食べてから約40年、ついに患者として認定された。
▽カネミ油症とは
カネミ倉庫製の米ぬか油にポリ塩化ビフェニール(PCB)や猛毒のダイオキシン類が混入し、多くの健康被害をもたらした。被害を訴えたのは長崎県五島市や福岡県を中心に計約1万4千人に上るが、厚生労働省によると、21年末時点での累計認定患者数は2355人。うち子ども世代は約50人いる。患者の診断基準には、発病条件の中に「油症母親を介して児にPCBなどが移行する場合もある」と明記されている。
被害者側は、同社や国らを相手に多くの法廷闘争を展開。被害者救済法ができたのは12年だった。患者に認定されると、カネミ倉庫から一時金として23万円を受け取る。健康調査に協力すると国が19万円、カネミ倉庫が年5万円と医療費自己負担分などを支払うことになった。また同法では新たに、認定患者と同居していた家族で、一定の症状のある人も認定されることになった。
患者の子どもでも被害を訴える人はいるが、直接食べた親世代に比べて血中濃度の数値は低く、認定されないケースが多かった。そうした状況を打開しようと、20年に被害者の支援団体は、子や孫らを対象とした健康調査を実施。一般成人よりも、油症特有の症状である腰痛や肩こりなどを訴える人の割合が高かった。被害者側は次世代の救済を求める要望書を国に提出。21年に国も初めてとなる全国調査を始めた。
▽ずさんな対応、国への強い不信感
「今まで国は2世の被害を見て見ぬふりをしてきた。今回の調査が認定につながるのか疑問」と話すのは森田さんの長女(43)。10代のころから、皮膚症状や婦人科系の疾患に苦しんできた。母とともに油症検診を受けると、ダイオキシン類の血中濃度の数値は51・68。基準に達したのになぜか認定されず、抗議しても覆らなかった。2回目も49・48で棄却。3回目、一番低い45・6だったが、これまでの結果を総合的に見て認定すると知らせがあった。「ずさんな認定。基準はあってないようなものだ」と感じた。
小さい頃から突然のめまいに襲われ、乾癬で皮膚がぽろぽろとはがれた。安子さんによると、長男も検診を受けたが、認定は長女だけ。長男の数値は35ほどだが、皮膚症状は一番重い。ひどい時には全身やけどのように皮膚が荒れ、病院通いが欠かせない。次世代への調査が始まった一方、あるのは国への強い不信感。調査が直ちに認定基準の変更につながるとは思えず、3人それぞれ今回の参加は見送ったという。
3世への不安もある。21年5月、次女のもとに赤ちゃんが生まれた。安子さんは「孫が生まれてうれしい気持ちと同時に怖い気持ちも押し寄せた」。新生児のころ、油症の症状の一つである「目やに」が出た。医師に聞くと「めずらしい」という。次女は子どもへの影響を考え、母乳をあげていない。「孫に何かあったらどうしよう」。常に不安が付きまとう。
安子さんは「生まれながらに被害を受け継いでしまった次世代については、無条件で患者として認定すべき」と強調。長女も「認定、未認定に限らず2世もたくさんの不調を抱え、日々を生きている」と訴える。
▽透明性のある認定と適切な補償を
国の次世代調査を担う「全国油症治療研究班」は2月、調査の中間報告を発表した。回答したのは子ども322人、孫66人。倦怠(けんたい)感や頭痛を訴える人はそれぞれ約4割いた。先天性疾患である口唇口蓋(こうがい)裂や心臓の壁に穴が開いていた人もいた。
回答者には今後油症検診を受けてもらい、客観的なデータを集め、患者認定基準の見直しを国などと協議する。これまで血中濃度の数値が低く未認定だった二世からは期待の声が上がる一方、そもそも医学的な基準にとらわれない認定の拡大を求める声もある。
高崎経済大の宇田和子准教授(環境社会学)は「医学的根拠を必須とする以上、未認定患者が産み出され続ける」と指摘。同様の公害が起きた台湾では、母親が認定患者であれば専門家の診断なしに認定されるという。国は「医学的エビデンスがないと認定できない」という一方で、12年の被害者救済法では医学的根拠を用いていない「同居家族認定」を認めた。「画期的な判断だった。国は自らタブーを破っている」と指摘する。
脆弱な補償体制も大きな問題だ。水俣病では患者に認定されると原因企業のチッソから一時金1600~1800万円が支払われており、大きな差がある。油症患者の医療費についても、カネミ倉庫が支払える範囲で行われており、長年患者が求めている入院中の食費は保険診療の適用外を理由に支払われていない。会社の経営が悪化しないよう、患者側が我慢を強いられているとの指摘がある。今後、多くの次世代が患者認定された場合、さらなる補償の圧迫につながる可能性もある。
国は補償に対し「汚染者負担」の原則を掲げる一方で、毎年カネミ倉庫に政府備蓄米の保管を委託して経営を支える。宇田准教授は「既に原則は崩れており、国は患者の要求が満たされていない以上、どうしたら実現できるのか積極的に考えるべき」と強調。その上で「今の状況では次世代が患者として名乗り出るメリットがあまりにも少ない。被害の全容を解明するためには、透明性のある認定と適切な補償が欠かせない」と訴えた。